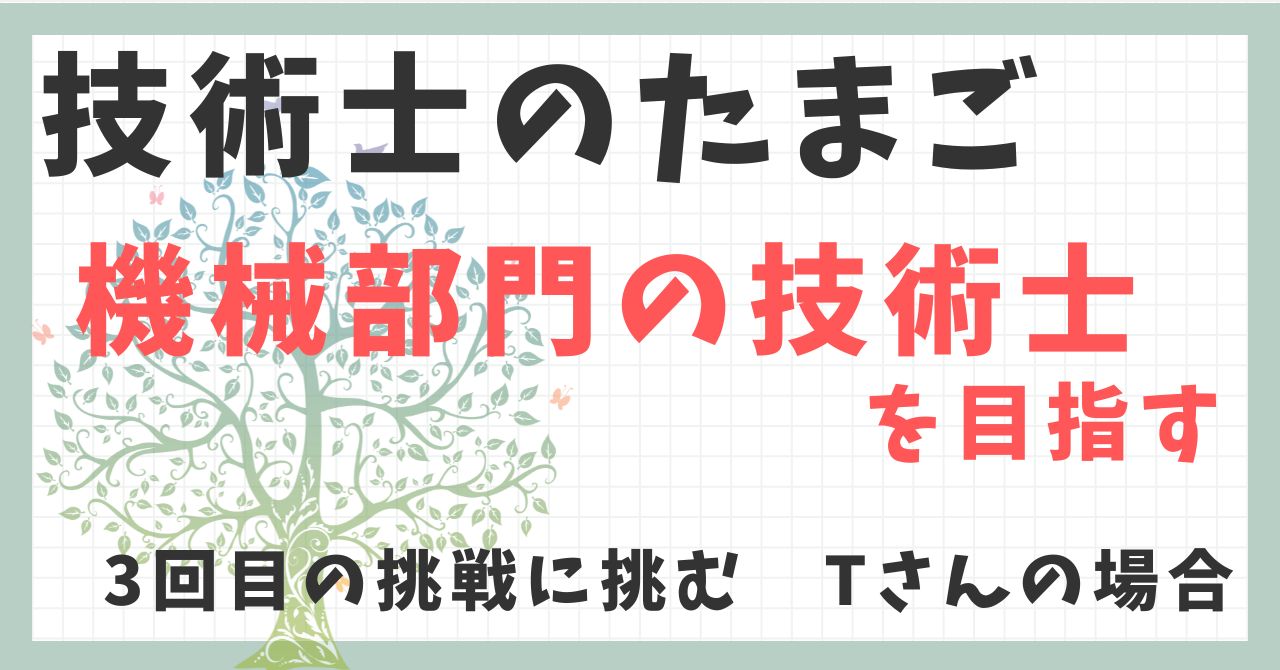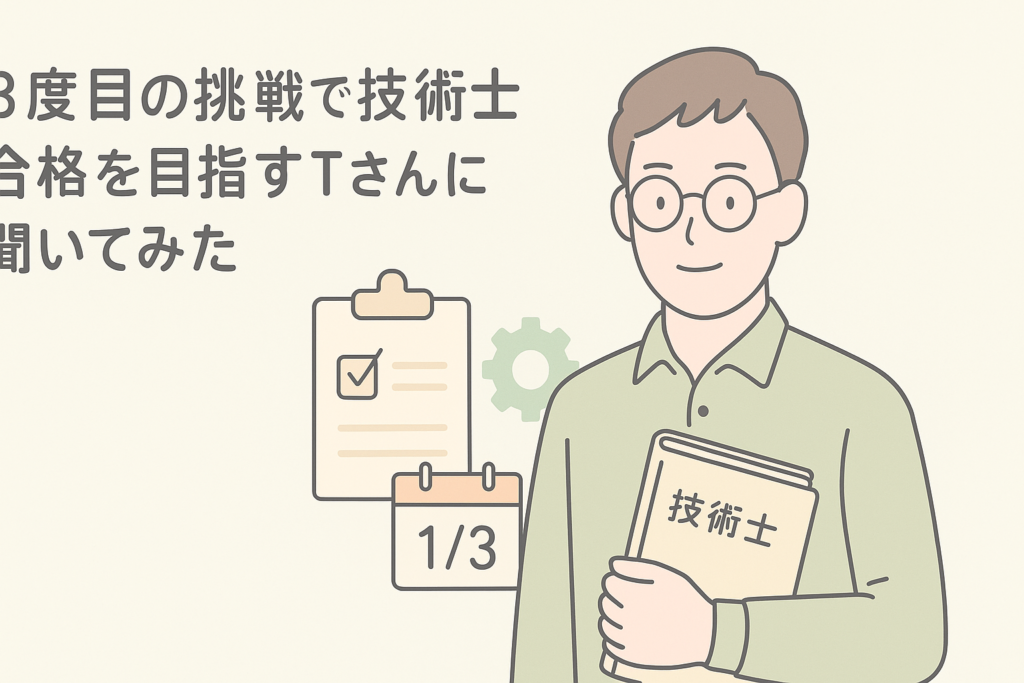
- 3度目の挑戦で技術合格を目指すTさんに聞いてみた
- 技術士を目指そうと思ったきっかけは何ですか?
- 現在のご職業や専門分野と、技術士資格を取得しようと思った背景はどのように結びついていますか?
- どのような勉強方法をしていますか?
- 独学ですか? 講座などは利用されていますか?
- モチベーションを維持するために心がけていることは何ですか?
- 過去に不合格など挫折を経験したことはありますか? ある場合は、どのように気持ちを立て直しましたか?「あきらめなかった理由」はなんですか?
- 実際に受けてみて、技術士試験のどんなところに難しさを感じましたか?
- 試験制度や出題傾向について、どのような情報収集を行っていますか?
- 技術士として“こうなりたい”という将来像や、夢はありますか?
- 合格に近づくために改善した点や、次回への意気込みを教えてください。
- これから技術士試験に挑戦しようとしている方に、伝えたいことはありますか?
- 最後に
3度目の挑戦で技術合格を目指すTさんに聞いてみた
機械メーカーで働く40歳のTさん。奥様と小学生のお子さん2人と暮らし、“平凡”を自称する彼ですが、その目標は大きく「技術士(機械部門)合格」。試験にはすでに2回挑み、次はいよいよ3回目を迎えます。
試しで臨んだ1回目、筆記で苦戦した2回目を通じて「自分の弱点」や「勉強の仕方の甘さ」を痛感したというTさん。今回はそんなTさんに、どんな経緯で技術士を志し、どのように学習法を改め、さらに次回に向けてどんな気持ちで挑もうとしているのか伺いました。
技術士を目指そうと思ったきっかけは何ですか?
機械メーカーに就職してから約十年、開発や設計に携わる中で、「もっと幅広いプロジェクトに技術的な意見を出せる存在になりたい」と思うようになったのが一番のきっかけですね。
機械設計技術者試験1級は持っていましたが、「もう一歩上の資格は?」と考えた時に、権威があり社会的信用度も高い技術士が浮かびました。
現在のご職業や専門分野と、技術士資格を取得しようと思った背景はどのように結びついていますか?

私は機械メーカーで新製品の設計や既存製品の改良などを担当しています。その過程で、例えば強度計算や材料選定、コストダウンの提案など、理論と実践の両方を行ったり来たりする作業が必要になります。また、より総合的な知見が求められる場面も多い。たとえば「この部品の設計変更が生産ライン全体にどう影響するか」など、システム的な視点が大切。
技術士資格は、そういった総合力が試される資格だと認識しています。自分が身に付けた経験や知識をさらに体系化し、多角的に応用できる技術者になりたいとおもっています。
どのような勉強方法をしていますか?
最初に受けた1回目は、ほぼ準備なしでした。「どんな問題が出るのかな?」と雰囲気を掴むための受験でした。2回目は市販の参考書や過去問を購入して独学で対策しましたが、正直言うと「やっているつもり」の状態だったと思います。
3回目となる今回はオンラインの講座を受講してみました。動画を見つつ、自分でアウトプットする時間を徹底的に増やしています。過去問の解答例をただ書き写すのではなく、「自分の言葉でどこまで説明できるか」を意識しながら解答論文を書いています。そのうえで、模範解答との比較や添削結果を受けて足りない要素をあぶり出すようにしています。
また、出題傾向に合わせて数パターンの論文をいくつか用意して挑む準備をすすめています。
独学ですか? 講座などは利用されていますか?
今はオンラインの講座を利用しています。独学でもある程度いけるかなと思っていましたが、やはり試験の傾向や論述の要領はプロの指導があると全然違う。(私はとにかく安くしたかったので色々調べてスタディングというオンライン講座にしました。)
自分で参考書を読んでも“分かった気”になるだけで、本当に理解できていなかった。講座では動画解説や添削指導があるので、勉強に対するモチベーションも維持しやすいです。
モチベーションを維持するために心がけていることは何ですか?
とにかくルール化することだと思います。私の場合は、朝は早起きして30分、夜は子どもの寝かしつけの後に1時間など、少しでも勉強に集中する時間を確保しています。
もう一つは「合格後のイメージを具体的に描く」ことですね。技術士に合格したら、企業との交渉もスムーズになるし、ライターとしての執筆案件も「技術士が書くから説得力が違う」と喜んでもらえるはず。将来、独立した時には・・・と想像するとワクワクするんです。
過去に不合格など挫折を経験したことはありますか? ある場合は、どのように気持ちを立て直しましたか?「あきらめなかった理由」はなんですか?
2回目は相当頑張ったつもりだったので、筆記試験で不合格になったときは「自分に才能がないのか」と落ち込みました。それでもあきらめなかったのは、「1回目に比べれば、明らかに手応えがあった」という感覚があったからです。つまり、ゼロから一歩踏み出せた。そうであれば、もっと効率的な勉強法を取り入れて、弱点を補強すれば合格へ近づけるはずだと前向きに考えられました。
また、子どもに「パパ、また勉強してるの?」と言われると、逆に燃えます(笑)。自分が努力している姿を見せることで、何かを成し遂げる背中を子どもたちに示したい。そんな想いもあるかもしれません。
実際に受けてみて、技術士試験のどんなところに難しさを感じましたか?
とにかく筆記試験が本当に大変ですね。問題文を読んで知識を羅列するだけでは全くダメです。“課題の本質”や“社会的意義”などを織り交ぜながら、自分の経験を踏まえた回答を論理的に展開しなければいけない。その幅広さが技術士試験の真髄だと思います。
要するに、単なる暗記力ではなく「実際の業務や社会課題にどう結びつくか」を問われるので、日頃からニュースや業界動向をチェックして、考察する習慣が必要。
また、論文を手書きで書ききることも普段はやらないので大変でしたね。
試験制度や出題傾向について、どのような情報収集を行っていますか?
まずは過去問の分析が基本だとおもいます。各年度の出題傾向や配点、論述のテーマに共通するポイントをまとめて、自分の得意・不得意を洗い出しました。あとは、国省庁の白書などの資料です。私は機械部門なのでものづくり白書が取っ掛かりになりました。
技術士として“こうなりたい”という将来像や、夢はありますか?
目指しているのは、「実務経験に裏打ちされた説得力のあるエンジニア」ですね。今は機械メーカーの一員としてモノづくりをしていますが、将来的には技術コンサルや独立も視野に入れています。副業でライターをしているのは、自分が得た知識やスキルを言語化する能力を鍛えたいからというのも大きいんです。
もし独立できたら、「技術士×機械設計×ライター」の三位一体で、設計のアドバイスから技術的なドキュメント作成まで請け負える存在になりたいですね。社会や企業に対して、技術者目線と発信者目線の両面から価値を提供できる人材はまだまだ少ないと感じていますので、そこに自分ならではの強みがあると思っています。
合格に近づくために改善した点や、次回への意気込みを教えてください。

一番の改善点は「客観的なフィードバックを積極的に取り入れる」ことです。2回目までは、基本的に独学で「これでいけるだろう」と思ってしまいがちでした。でも実際は、論述問題の構成や事例の深堀りなど、プロの目線や合格者の目線を取り入れないと自分の回答がどこまで合格レベルに達しているのか分かりません。
オンライン講座の添削では、想像以上にダメ出しをされましたが(笑)、そのおかげで論述の組み立て方が劇的に変わりました。過去問の分析もしっかりやって、第三者に意見をもらうことで自分の弱点がハッキリ見えてきましたね。次は必ず合格したいですし、むしろ「ここまでやって落ちるわけにはいかない」という強い気持ちがあります。
これから技術士試験に挑戦しようとしている方に、伝えたいことはありますか?
どんな資格試験でも言えることですが、「一度試験を受けてみる」って意外と大事なんじゃないかと思います。私も1回目は試しで受けましたが、そのおかげで試験の流れや会場の雰囲気、論述の時間配分などがリアルに分かりました。知識をインプットするだけより、実際にアウトプットを経験することで見えてくる課題があります。
また、私の反省点ですが、早めに講座などを一度受けるべきだったと思います。
最後に
3回目の挑戦に臨むTさん。オンライン講座を活用しながら、これまでとは違うアプローチで弱点を補強しています。仕事と家庭、そして副業を並行しながらも、“合格後の姿をイメージする”ことがモチベーションを支える大きな力に。
技術士としての肩書を手にし、独立後は「機械設計の実務力」「ライティングの発信力」「資格による信頼感」を掛け合わせて活躍したい──Tさんの思いは、同じようにキャリアアップを目指す受験者たちの背中を押してくれるでしょう。何より、「不合格は過程の一部であり、失敗からいかに学び取れるかが合否を分ける」と語るその姿勢こそが、確実に合格へ近づくためのカギになりそうです。
弊サイトでは、技術士を目指す方の勉強の励みになるように現役技術士や技術士を目指してる方にアンケートインタビューをおこなっています。
アンケートに応えていただける方はご連絡お待ちしております。※少ないですが報酬として3,000円お支払いいたします